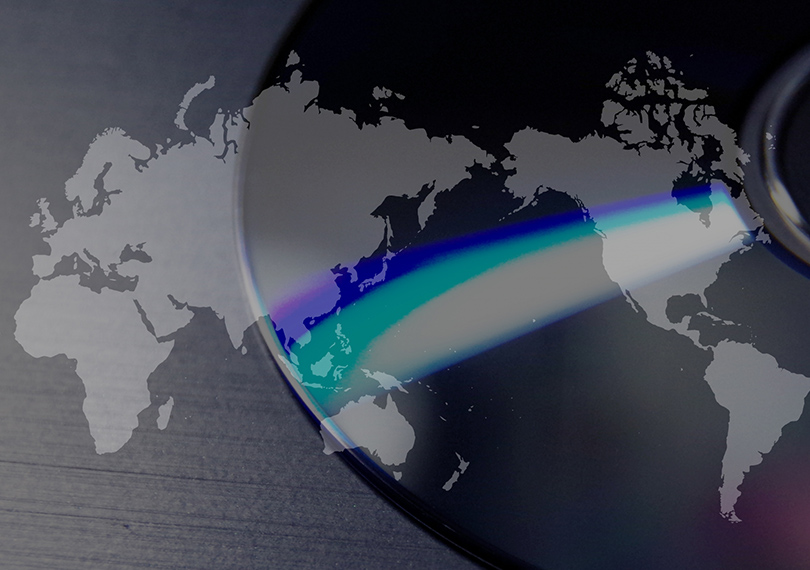研究所案内
コラム
2018.10.5 更新
スーパーが直面する「客数減」の考察
池田 満寿次
公益財団法人 流通経済研究所
昨今、気がかりなのがスーパーの減速ぶりだ。大都市圏で展開する一部のチェーンを除くと、既存店売上が前年水準を下回るケースが目立っている。
既存店の苦戦の要因を紐解くと、買い物客数の減少が作用している様子がわかる。筆者が、全国各地のスーパー計178店舗(※1)を対象に過去5年間の客数の推移を調べたところ、図表1のとおり1店舗あたりの買い物客数(年間)は年1-2%のペースで減少していることがわかった。とくに2017年度は前年比3.5%減と減少幅が広がり、底打ちの兆しが見えていない。対象店舗の総客数はこの5年間で1割も減少したほか、5年前と比較して客数が増えた店舗は178店中わずか34店(全体の19%)にとどまった。

近年、国内の景気・消費動向はおおむね堅調であることを踏まえると、足元で進む客数減は構造的な理由に依るものが大きいと言える。客数減の要因をめぐっては、店舗商圏における①人口・世帯数の減少、②高齢者の比率の増加、③他社との競合増――といった要因が作用していると考えられる。②は商圏の居住者の胃袋が徐々に小さくなることを意味するものであり、食品を主体に扱うスーパーにとってはボディーブローのように効いてくる。
前出のデータを地域別に見ると、とくに地方部での客数減が目立つ。人口・世帯数が伸長している東京エリアの店舗は客数がほぼ横ばいなのに対し、人口減や高齢化が進む北海道・東北はこの5年間で15%も減少した。地域によって明暗がはっきりと分かれているのである。
客数減が目立つ地方では、③に挙げた他社との競合増による影響も大きいと推察する。とくに競合することが増えているのはドラッグストアだろう。近年、ドラッグストアは地方や郊外での出店ペースを加速している。集客の一環で食品を値ごろ感のある価格で販売強化していることから、日増しにスーパーを脅かす存在になっている構図だ。
こうした結果、地方では食品の購入先としてドラッグストアが身近な存在になっている様子が浮かび上がる。全国の消費者パネルによる食品の購入先を調べると(※2)、地方ほどドラッグストアの利用が多い傾向があった(図表2)。たとえば東京圏では食品購入におけるドラッグストアでの支出割合が6.3%だったの対し、九州では同14.8%、北陸甲信越は同11.8%と、有力ドラッグストアが居並ぶ地域ではその支出割合が上昇していたのである。

ドラッグストアが主力商材とする医薬品や化粧品、日用品は購入頻度が多くない。そこで食品を筆頭に、取り扱うカテゴリーを広げることで、集客強化を図ってきた。いまや郊外のドラッグストアに足を運ぶと、下着類や調理器具、カー用品と様々なアイテムを店内で見かける。こうした結果、「ドラッグストアに行けば、一通り揃う」といた認識を浸透させている。
ちなみに研究協力先のスーパーとドラッグストアを対象に、近似する店舗タイプでの品揃えを比較したところ、ドラッグストアでは1日1点以上の販売実績があったカテゴリー数が440あったのに対し、スーパーは290カテゴリーにとどまっていた。この数字の差は、ドラッグストアが生活者のさまざまな買い物ニーズに応えていることを物語る。
スーパーは近年、日用品など非食品分野の売場を縮小し、売場のリストラクチャリングを進めてきた。生活者の買い物ニーズに応えるというよりも、売場の販売効率を優先してきた形だ。ただ客数減は、売場の商品回転を悪化させ、食品の鮮度低下を招きかねないほか、店舗から活気をも奪う。「客数を増やす」という視点から、スーパーの店舗全体で何ができる得るのかを真正面から考える時期に差し掛かっている。
※1 流通経済研究所が扱う「全国POSデータサービス(NPIレポート)」のデータ収集店舗のうち、5年以上営業するスーパー店舗(178店舗)を対象とした。
※2 マクロミルグループの消費者購買履歴データQPRで扱う消費者パネル約3万5千人(全国)の2017年下期実績(7-12月)を分析。食品の購入実績に生鮮・惣菜は含まれない。